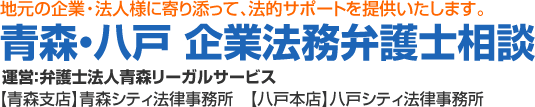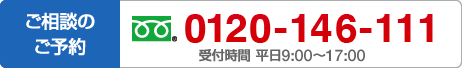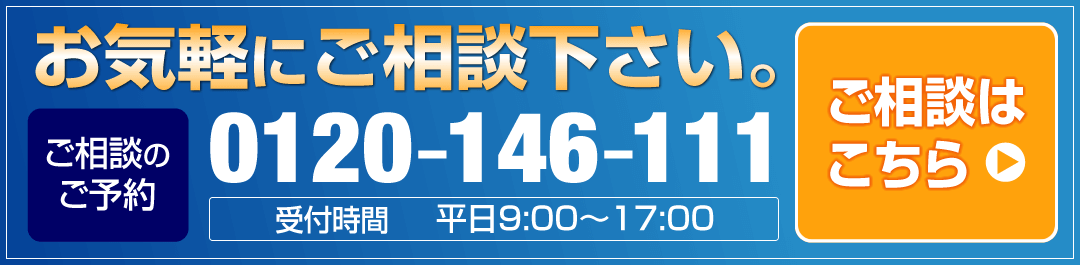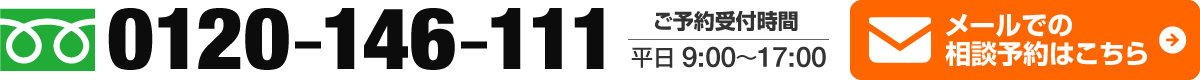1 製造業でよくあるパワーハラスメントとは?

パワーハラスメント(いわゆるパワハラ)は、上司と部下との間のみならず、同僚、あるいは自分の部下が相手であっても成立する可能性があります。
また、パワハラの態様として、一般的には、殴打するなどの身体的な攻撃や侮辱するといった精神的な攻撃の他、無視などの人間関係からの切り離しといった態様が考えられます。
この点、製造業では、危険物等の取扱い、危険を伴う機械・設備等の使用、危険場所での作業など、リスクを伴う業務も多いことから、その指導にも熱が入りやすいといえるでしょう。
そのため、製造業でパワハラが問題となった事例を見ていると、上司からの指導・叱責の際の表現や、その方法が不適切であると評価されているものが多いように見受けられます。
以下では、一般的なパワハラの定義等を確認しつつ、製造業におけるパワハラ従業員への対処方法について、具体的にご説明させていただきます。
2 そもそもパワハラに当たる言動とは?
(1)法律上のパワハラの定義
パワハラの定義については、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(労働施策総合推進法)で定められています。
そして、法律上、パワハラとは、職場において行われる①優越的な関係を背景にした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されることをいうと定義づけられています。
この定義について若干補足しますと、
・①の「優越的な関係」というのは、上司と部下の関係のみならず、同僚または部下が業務を行う上で必要な知識や経験を有しており、当該同僚または部下の協力を得ることができなければ業務を円滑に行うことが出来ないような場合にも、当該同僚または部下との間で「優越的な関係」が生じていると評価できます。
・②の「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」というのは、業務の目的や性質、言動の回数や内容、手段に照らして具体的に判断されることとなります。
・③の「就労環境が害される」というのは、当該言動により、労働者が身体的または精神的に苦痛を与えられるなどして、当該労働者が就業するうえで看過できない程度の支障が生じることをいい、平均的な労働者の感じ方を基準にして判断されます。
(2)一般的なパワハラの例
厚生労働省は、一般的なパワハラの例として、次の6つを挙げています。
|
6つの類型
|
具体例 |
|
㋐身体的な攻撃
|
暴行、傷害など |
|
㋑精神的な攻撃
|
脅迫、名誉毀損、侮辱など |
|
㋒人間関係からの切り離し
|
仲間外し、隔離、無視など |
|
㋓過大な要求
|
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制など |
|
㋔過小な要求
|
合理性なく能力とかけ離れた程度の仕事を命じる、仕事を与えないなど |
|
㋕個の侵害
|
私的なことに過度に立ち入るなど |
ここで、注意しておくべきこととしては、㋐、㋑、㋒のような言動は、比較的業務の適正な範囲内のものではないと認定しやすい一方で、㋓、㋔、㋕のような言動に関しては、業務の適正な範囲内か否か、認定が難しいケースもあると考えられるため、慎重に判断する必要があるでしょう。
3 製造業におけるパワハラの例
今回は、製造業を営む企業においてパワハラが問題となった事例をいくつかご紹介させていただきます。
(1)メイコウアドヴァンス事件(名古屋地方裁判所平成26年1月15日判決。金属琺瑯加工業。)
この事案は、労働者がパワハラを受け、その後うつ病となり、自殺をした事案です。
労働者が仕事でミスをするたび、社長が労働者に対し、「てめえ、何やってんだ」「どうしてくれるんだ」「ばかやろう」などの暴言や、殴る蹴るなどの暴行を繰り返し行うのみならず、自殺直前の時期には、労働者に対して退職届を書くように強要し、社長が書いた退職届の下書きには、会社に与えた損害に関しては、一族をもって返済する旨記載されており、その金額としては、1000万~1億円と記載されていました。
この事案では、社長の各言動は、労働者の仕事上のミスに対する叱責の域を超えて、労働者を威迫し、激しい不安に陥れるものと認められ、不法行為に該当するとの判断がなされました。
(2)サントリーホールディングスほか事件(東京高等裁判所平成27年1月28日判決。飲料製造販売会社。)
この事案は、主に以下の言動が、パワハラとして不法行為に該当するかが問題となりました。
①上司が、作業ミスを繰り返す部下に対して、「新入社員以下だ。もう任せられない。」「何で分からない。おまえは馬鹿。」等と叱責した。
②上司が、うつ病を発症、休職を願い出た部下に対して、“休養については有給休暇を消化してほしい”“当該部下が別の部署に異動になる予定があるが、休みを取るならば異動の話は白紙に戻さざるを得ず、当該上司の下で仕事を続けることになる”などと述べた。
裁判所は、このような上司の言動は、部下に対する注意・指導として許容される限度を超え、不法行為を構成するものと認定しました。
(3)アークレイファクトリー事件(大阪高等裁判所平成25年10月9日判決。医薬品製造販売会社。)
この事案は、派遣労働者として就労していた労働者が、派遣先の従業員らから受けた言動が問題となりました。
派遣先の従業員が、当該労働者の所有している車両に危害を加えるような言動を繰り返していたことや、当該労働者の業務中のミスに対し、「殺すぞ。」「あほ。」などと述べたことに関して、従業員によるパワーハラスメントがあったとして、会社の使用者責任の限度で、不法行為の成立を認めました。
4 企業がパワハラ従業員を放置するリスク
パワハラの問題が発生すると、企業は、パワハラの被害に遭った労働者から、損害賠償を請求されるリスクがあります。
また、職場でパワハラが行われている場合には、従業員らに対して心理的な悪影響を及ぼし、職場環境を悪化させてしまいます。
その結果、従業員らのモチベーションの低下、業務効率の悪化、優秀な人材の離職などの問題が発生してしまいます。
そのため、企業がパワハラ従業員を放置することのリスクは、非常に大きいものといえるでしょう。
特に、令和4年(2022年)4月1日より、労働施策総合推進法において、パワハラ防止措置が全企業を対象に義務化されています。
従前から、パワハラの被害を受けた労働者から、企業は損害賠償の請求を受けてきていましたが、パワハラ防止のための制度が適切に構築されていたのか、構築された制度が適切に運用されていたのか、といった観点からも判断されることとなり、企業におけるパワハラに対する取り組みは厳しく評価されることを自覚し、適切な措置を講ずる必要があるといえるでしょう。
5 製造業におけるパワハラ従業員への対処法
製造業は、業務における指導に熱が入りやすい業種であると考えられます。
どの業種にも該当しうることではありますが、製造業においても、昨今の人材不足は否定できないのではないかと思います。
そのため、パワハラ従業員がいると疑われる場合、優秀な人材の流出や、損害賠償のリスクを免れるためにも、速やかに対応していく必要があります。
具体的には、事実関係の調査・確認を行い、その結果、パワハラの事実があったものと認められる場合、加害者に対して、就業規則に基づく懲戒処分や配置転換などの適切な措置を講じていくこととなります。
他方で、被害者に対しては、加害者への処分の内容を報告するとともに、今後の再発防止措置を徹底することを説明したうえで、必要に応じて謝罪などの対応を取ることとなります。
6 製造業におけるパワハラ従業員問題は当事務所にご相談ください
製造業は、業務における指導に熱が入りやすい業種であり、パワハラに関するトラブルも少なくありません。
パワハラについては、事後的な対応も大切ではありますが、トラブルを発生させないための予防策を適切に講じておくことが非常に大切です。
当事務所では、パワハラに関する事実関係の調査・確認、加害者への懲戒処分などのサポート、被害者への対応のサポート、損害賠償請求を受けた場合の示談交渉・訴訟への対応のように、トラブルが発生してしまった後の対応はもちろんのこと、パワハラの予防策や再発防止策の構築のサポート、社内研修の講師、社外の相談窓口など、充実した法的サービスを提供させていただくことが可能です。
製造業におけるパワハラ従業員に関する問題についてお困りの企業・法人様がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。
製造業の解決事例はこちら
製造業についてはこちらもご覧下さい
●製造業を営む企業様へ
●製造業におけるパワハラ問題を放置するリスクと対処法を弁護士が解説
●製造業で注意すべき労務問題と対応について弁護士が解説
●製造業における残業代請求対応トラブルについて弁護士が解説
●製造業における雇用トラブルとは?弁護士が解説
●製造業におけるクレーム対応について弁護士が解説
●製造業で企業が注意すべき従業員の労働災害について弁護士が解説