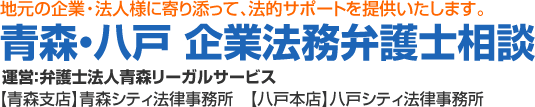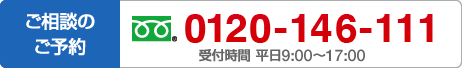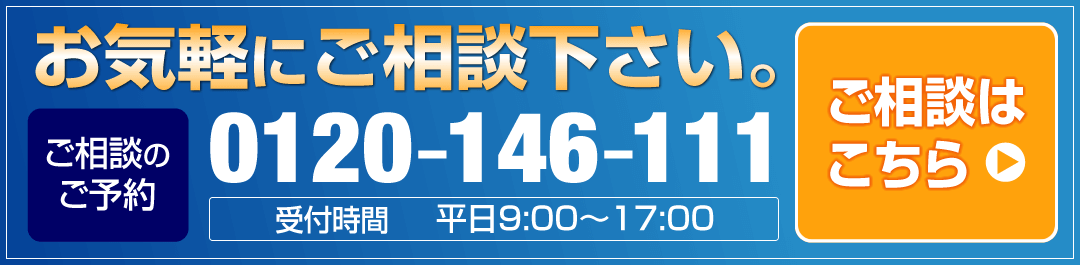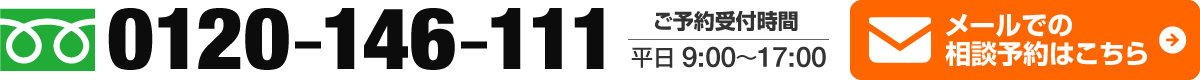1 製造業におけるクレームトラブルの特徴

製造業におけるクレームトラブルの特徴は、製品の品質、価格、サービス対応など、多岐にわたる原因で発生することが挙げられます。
製品の品質に関するクレームトラブルは、検査工程での見落としや、製造過程での不具合により、顧客に不良品を届けてしまうことで発生します。
また、耐久性が不足した製品を届けてしまい、使用中に故障したり、破損したりして、顧客からクレームを受ける場合もあります。
さらに、製造過程で異物が混入してしまった場合には、異物の種類や大きさによっては、製品の安全性や品質に重大な影響を与え、深刻なクレームトラブルを引き起こす危険性があります。
製品の価格に関するクレームトラブルとしては、価格を誤って表示してしまい、顧客からクレームを受けるケースがあります。
また、契約の時に提示された価格以外に追加費用が発生した場合も、顧客からのクレームにつながる可能性があります。
サービスに関するクレームトラブルとしては、クレームに対する対応が遅い場合に、顧客からの不満が高まり、さらなるクレームを引き起こす可能性があります。
また、クレーム対応が不適切である場合には、その顧客からの信頼を失うだけでなく、企業の評判を落とすことにつながりかねません。
2 正当なクレームと理不尽なクレームの違い
製造業における正当なクレームと理不尽なクレーム(カスタマーハラスメントを含む)の主な違いは、要求の妥当性と手段の妥当性です。
正当なクレームは、製品や価格、サービスに関する不具合や不満を、社会一般の常識に照らして適切な方法で伝えるものです。
一方、理不尽なクレームは、要求内容が不当であったり、要求の手段や態度が不適切であったりするものです。
正当なクレームと理不尽なクレームの違いを、目的、要求の妥当性、手段・態度の妥当性、影響、具体例の各項目で整理すると、次のとおりとなります。
製造業におけるクレーム対応においては、正当なクレームと理不尽なクレームを区別し、それぞれに応じた適切な対応をすることが重要となります。
| 正当なクレーム | 理不尽なクレーム | |
| 目的 | ・問題解決や改善を求める | ・嫌がらせ ・金銭や過剰なサービスを引き出す ・精神的に相手を追い込むなど |
| 要求の妥当性 | ・製品や価格、サービスに関する不具合や不満など、社会一般の常識に照らして妥当な範囲の要求 | ・法的・社会的に妥当性を欠く過度な要求 ・精神的苦痛を与える要求 |
| 手段の妥当性 | ・社会一般の常識に照らして適切な方法で伝える | ・暴言、脅迫、威圧的な態度、執拗な要求などの不適切な手段や態度 |
| 影響 | ・企業にとって改善の機会となる | ・従業員の精神的な負担 ・業務妨害 ・企業のイメージダウン |
| 具体例 | ・製品の欠陥や不具合に対する指摘 ・契約内容に関する疑問や不満 ・サービス品質に関する改善要求 ・接客・電話対応におけるサービス態度に対する不満 |
・些細なミスに対する過大な要求や特別対応の要求 ・要求内容をコロコロ変える ・不合理な内容の念書や誓約書などの一筆の要求 ・暴言や脅迫、威圧的な態度 法的根拠のない過大な金銭要求 ・精神的な苦痛を与えるような言動 |
3 製造業におけるクレーム対応の流れ
製造業におけるクレーム対応の流れは、大きく分けて「事実の把握」、「原因究明」、「対策の立案・実施と再発防止」、「顧客対応」のステップで構成されます。
以下に具体的な流れを説明します。
(1)事実の把握
以下の項目で、事実を把握していきます。
①クレーム内容を確認する
⇒顧客からの連絡内容を正確に把握し、どのような状況で、どのような問題が発生したのかを明確にします。
②現品を確認する
⇒可能であれば、現品(クレーム対象の製品そのもの)を回収し、仕様書と比較するなどして詳細な確認を行います。
③工程履歴を調査する
⇒製品が製造されてから顧客の手に渡るまでの工程をさかのぼり、どこでどのような作業が行われたかを調査します。
(2)原因の究明
発生した問題の原因を特定するために、いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように(5W1H)を意識しながら分析を行います。
製造、品質管理、設計などで部署が異なる場合には、関係する部署と連携し、情報を共有しながら原因を究明します。
また、必要に応じて、社内外の専門家の意見を求め、原因究明をより確実なものにします。
(3)対策の立案・実施、再発防止策
分析によって特定された根本原因に基づいて、具体的な対策を立案し、速やかに実施します。
根本原因に対する対策だけでなく、再発防止策も合わせて策定します。
(4)顧客対応
製造業におけるクレーム対応の最重要課題は、顧客対応です。
顧客対応においては、初期対応が極めて重要であり、正当なクレームなのか、理不尽なクレーム(不当要求)なのか、両方の可能性を考慮しつつ、初期対応を行います。
その際の注意事項を挙げると、次のとおりとなります。
〇話の聞き取りに徹し、その顧客の話の趣旨および目的の明確化に努める。
〇窓口となる担当者を決め、顧客との連絡・やり取りはその担当者に一本化する。
〇面談は複数人で対応する。
〇早い段階で現品を確認するなどして事実関係の確認・明確化に努める。
〇顧客から即答や約束を求められてもこれには応じず、念書等の一筆を求められても応じない。
〇現品などの客観的資料の入手に努める。
〇対応時の内容を、録音やメモ等により社内で共有する。
〇顧客の要求内容のほか、要求態様も記録し、社内で共有する。
事実の把握、原因の究明で得られた情報を基に、正当なクレームなのか、理不尽なクレームなのかを見極めます。
正当なクレームは、会社が受け入れるべきものであり、製品やサービスの品質を向上させるヒントでもあるので、企業としては誠実かつ真摯な対応が基本となります。
そのため、顧客との面談では、原因、対策、再発防止策などについて丁寧に説明・報告し、顧客の信頼回復を図ります。
他方、理不尽なクレームに対しては、早期かつ効率的に対応を終了させてしまうことが必要です。
回答内容も一本化し、同じ窓口・担当者で同じ回答を繰り返します。
なお、担当者を孤立させないように企業全体でフォローすることは忘れてはなりません。
製造業におけるクレーム対応は、製品の品質向上だけでなく、顧客からの信頼を回復し、企業ブランドを維持するために非常に重要です。
正当なクレームに対しては、迅速かつ丁寧な対応を心がけ、顧客の満足度向上に努めることが求められます。
4 クレームトラブルの未然防止策
製造業におけるクレームトラブルの未然防止策としては、「原因の解明と対策の実施」、「ルールの見直しと徹底」、「作業員の教育とコミュニケーションの活性化」、「定期的なチェック」が挙げられます。
(1)原因の解明と対策の実施
クレーム発生時には、原因を徹底的に究明します。
そして、類似のトラブルの発生を未然に防ぐための対策を講じます。
一時的な対策としては、検査工程におけるチェックシートの導入やチェック体制の強化などが考えられます。
恒久的な対策としては、作業手順の見直し、関連する作業員及び管理者への再教育、定期的な監査などが考えられます。
(2)ルールの見直しと徹底
作業マニュアルを整備し、作業員が誰でも同じように作業できるように標準化することが考えられます。
その作業マニュアルは、現場の意見を取り入れ、常に最新の状態に保つことが重要です。
そして、作業マニュアル、チェックリストなどを整備し、作業の標準化と見える化を進めます。
(3)作業員の教育とコミュニケーションの活性化
新人だけでなく、ベテランに対しても、定期的な教育を実施すことで、品質管理に関する知識や技術を向上させ、不良品の発生や異物混入のリスクを低減できます。
また、教育の中では、作業員一人ひとりが、品質に対する意識を高め、不良品を出さない、異物混入を発生させないという意識を徹底します。
また、活発なコミュニケーションを促し、作業員同士の情報共有や連携を強化します。
例えば、朝礼やミーティングなどを活用し、作業状況や問題点を共有することなどが考えられます。
そして、疑問や意見を口に出しやすい雰囲気を作り、モチベーションを維持していきます。
(4)定期的なチェック
定期的に作業状況や設備の状態をチェックし、異常の早期発見に努めます。
また、検査を徹底し、不良品や異物混入が発生しないように徹底します。
さらに、クレーム発生時には、迅速な初動対応と原因究明、再発防止策の実施を徹底します。
5 製造業のクレーム対応を弁護士に依頼するメリット
製造業におけるクレーム対応を弁護士に依頼する主なメリットは、法的知識に基づいた的確な対応、精神的負担の軽減、そして理不尽なクレームへの毅然とした対応です。
弁護士は、正当なクレームと理不尽なクレームを区別し、適切な対応をすることで、企業を法的リスクから守ります。
また、対応窓口を一本化することで、担当者の負担を軽減し、本来の業務に集中できる環境を整えることができます。
(1)法的知識に基づいた的確な対応
弁護士は、法律の専門家として、クレームの内容や要求が正当かどうかを的確に判断し、状況に応じた適切な対応策を講じることができます。
これにより、理不尽なクレームに対しては毅然とした態度で臨むことができ、企業を法的リスクから守ることができます。
(2)精神的負担の軽減
クレーム対応は、担当者や経営者に大きな精神的負担を強いることがあります。
理不尽で、執拗なクレームが行われることもあり、担当となる従業員を心身共に疲労させ、人材の離職につながることもあります。
弁護士に依頼することで、対応窓口を一本化し、対応を全て任せることができます。
これにより、担当者は本来の業務に集中でき、精神的な負担を軽減することができます。
従業員にしてみれば、いつでも法律の専門家である弁護士に相談できる環境や機会が確保されているというだけでも、精神的な負担が大きく軽減させ、各従業員の生産性を向上させます。
(3)理不尽なクレームへの毅然とした対応
弁護士は、理不尽なクレームに対して、法的手段を視野に入れた対応をすることができます。
すなわち、裁判の見通しや金銭面、労力面を踏まえて、解決方法を提案し、企業にとって最善の利益を確保できる選択肢を選ぶことができます。
また、内容証明郵便の送付や、場合によっては民事訴訟や、理不尽なクレームに対する刑事告訴など、状況に応じた適切な措置を講じることができます。
(4)紛争の予防と解決
弁護士は、契約書等の整備など、クレームを未然に防ぐためのアドバイスも行います。
また、万が一紛争が発生した場合でも、交渉から裁判までを一貫してサポートし、早期解決を目指します。
さらに弁護士は、クレーム対応に関する社内マニュアルの作成をサポートし、組織としてのクレーム対応能力を向上させることができます。
6 製造業におけるクレームトラブルは当事務所にご相談ください
製造業におけるクレーム対応の最重要課題は顧客対応であり、顧客に対する初期対応が極めて重要となります。
そして、ここでは、事実の把握、原因の究明で得られた情報を基に、正当なクレームなのか、理不尽なクレームなのかを見極め、対応を行う必要があります。
この点で、弁護士は、法律の専門家として、クレームの内容や要求が正当かどうかを的確に判断し、状況に応じた適切な対応策を講じることが可能です。
そのため、クレームが発生したら、トラブルに発展する前に、できるだけ早く、弁護士に相談することが重要です。
当事務所では、クレーム対応に関するご相談を承っております。
製造業の皆様からのご相談も多く、お客様の状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。
製造業におけるクレームトラブルは、当事務所にご相談ください。
製造業の解決事例はこちら
製造業についてはこちらもご覧下さい
●製造業を営む企業様へ
●製造業におけるパワハラ問題を放置するリスクと対処法を弁護士が解説
●製造業で注意すべき労務問題と対応について弁護士が解説
●製造業における残業代請求対応トラブルについて弁護士が解説
●製造業における雇用トラブルとは?弁護士が解説
●製造業におけるクレーム対応について弁護士が解説
●製造業で企業が注意すべき従業員の労働災害について弁護士が解説