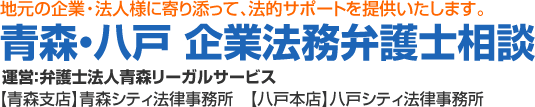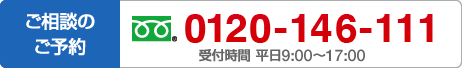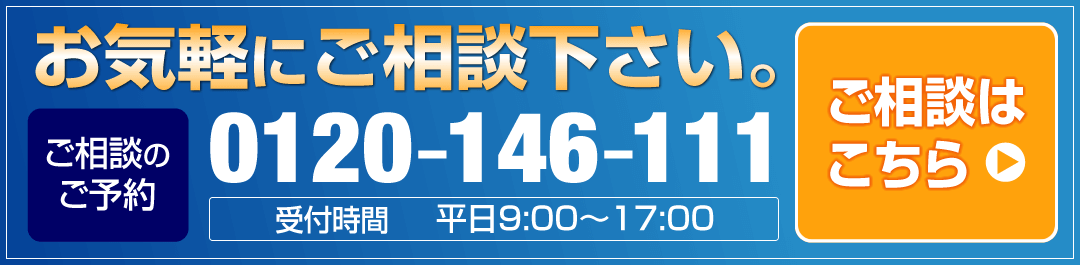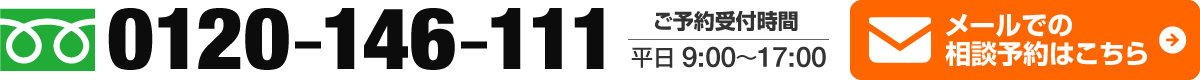この記事を書いた弁護士

弁護士・木村哲也
代表弁護士
主な取扱い分野は、労務問題(企業側)、契約書、債権回収、損害賠償、ネット誹謗中傷・風評被害対策・削除、クレーム対応、その他企業法務全般です。八戸市・青森市など青森県内全域の企業・法人様からのご相談・ご依頼への対応実績が多数ございます。
1 はじめに
近年、労働者の高齢化が進行し、後述する高年齢者雇用安定法の定めもあり、企業が定年後の高年齢従業員を再雇用することが一般的となっています。
そして、定年後再雇用の従業員の雇用の打ち切りをめぐり、労務トラブルが発生する例も増えています。
今回のコラムでは、定年後再雇用の従業員の雇い止めをする際の注意点について、ご説明いたします。
【関連コラム】
●定年後再雇用の拒否・雇い止めと賃金の引き下げについて
2 高年齢者雇用安定法と労働契約法
(1)高年齢者雇用安定法のルール
定年後の高年齢従業員の雇用に関連する法律として、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)があります。
高年齢者雇用安定法によれば、企業は60歳を下回る定年を定めることができないとされています(高年齢者雇用安定法8条)。
また、65歳未満の定年の定めをしている企業は、65歳までの安定した雇用を確保するため、①定年の引き上げ、②継続雇用制度の導入、③定年の定めの廃止のいずれかの措置を講じる法的義務があるとされています(高年齢者雇用安定法9条)。
この点、①定年の引き上げ、または③定年の定めの廃止を行うと、従前の労働条件による雇用が継続することとなるため、人件費がかさむ、世代交代に支障があるなどのデメリットがあります。
そのため、多くの企業では②継続雇用制度の導入が選択され、定年を迎えた従業員を一旦退職扱いとしたうえで再雇用し、1年ごとに契約を更新する有期雇用契約の形とするのが一般的となっています。
なお、高年齢者雇用安定法では、企業は65歳から70歳までの安定した雇用を確保するための措置を講じるように努めるものとされていますが(高年齢者雇用安定法10条の2)、あくまで努力義務であり、法的義務ではありません。
(2)労働契約法のルール
有期雇用契約では、企業側が期間満了後に契約を更新しなければ、雇い止めにより雇用関係が終了するのが原則です。
しかし、労働契約に関するルールを定める労働契約法という法律では、雇い止めに一定の制限が加えられており、これを雇い止め法理と言います(労働契約法19条)。
すなわち、反復して更新され期間の定めのない雇用契約と社会通念上同視できる場合(労働契約法19条1号)、および更新されるものと期待することについて合理的な理由がある場合(労働契約法19条2号)には、更新しないことについて客観的に合理的な理由があり、かつ社会通念上相当と認められる場合でなければ、雇い止めをすることはできないとされています。
この点、定年後再雇用においては、無期雇用契約と同視できる場合(労働契約法19条1号)は多くないと考えられます。
そのため、更新を期待することの合理的理由がある場合(労働契約法19条2号)の適否が中心となります。
3 65歳までの定年後再雇用者の雇い止め
前述のとおり、高年齢者雇用安定法9条により、企業には65歳までの安定雇用確保措置が義務付けられています。
そのため、65歳までの定年後再雇用者については、更新を期待することの合理的理由(労働契約法19条2号)があると認められることがほとんどです。
そうすると、65歳までの定年後再雇用者の雇い止めでは、更新しないことの客観的合理的理由と社会通念上の相当性を備えることが必要となります。
裁判例では、60歳で定年後に再雇用し、2回更新後に雇い止めをした事案で、更新を期待することの合理的理由があるとしたうえで、業績不振による人員削減を理由とする雇い止めには客観的合理的理由と社会通念上の相当性がないとして、雇い止めができないと判断したものがあります(福岡地方裁判所令和2年3月19日判決)。
また、非違行為がありけん責の懲戒処分を受けたことを理由に定年後再雇用の契約を解除した事案で、解雇事由等に該当する事情が認められなかったのであるから再雇用されるとの期待には合理的理由がある一方で、再雇用しないことには客観的合理的理由がなく、社会通念上相当とは認められないとして、解除を無効とした裁判例があります(富山地方裁判所令和2年11月27日判決)。
4 65歳以降の定年後再雇用者の雇い止め
前述のとおり、65歳以降の安定雇用確保措置は、あくまで努力義務であり、法的義務ではありません(高年齢者雇用安定法10条の2)。
そのため、更新を期待することの合理的理由(労働契約法19条2号)の有無は、個別の事情によります。
この点、65歳で定年後に1年間の有期雇用契約で再雇用された従業員の雇い止めをした事案で、企業側が再雇用にあたり選抜が必要であると説明していたこと、雇用契約書等に雇用延長を希望しても採用されない場合があると明記されていたこと等から、更新を期待することの合理的理由があるとは言えず、雇い止めを有効とした裁判例があります(東京地方裁判所平成30年7月18日判決)。
一方で、67歳で定年退職したタクシー運転手を1年間の有期雇用契約で再雇用し、1回更新後に道路交通法72条1項(交通事故発生日時等の報告義務)および17条2項(歩道等の手前における一時停止義務)違反を理由に雇い止めをした事案で、①当該企業のタクシー運転手のうち70歳以上の者が16%以上いること、②当該社員が昭和57年からタクシー運転手として勤務していること、③定年後に雇用契約書を作成しないまま1回更新していること等から、69歳の当該社員についても体調や運転技術に問題が生じない限り更新されると期待することに合理的理由があるとしたうえで、上記の道路交通法違反を理由に雇い止めをすることは重すぎるとし、雇い止めの客観的合理的理由および社会通念上の相当性は認められないとした裁判例があります(東京地方裁判所令和2年5月22日判決)。
また、定年後再雇用の事案ではありませんが、66歳で有期雇用した従業員を1年ごとに3回更新した後に雇い止めをした事案で、求人票の雇用期間欄には「契約更新の可能性あり(原則更新)」と記載されており、就業規則には年齢による更新上限や定年制の規定がなく、会社側から雇い止めの可能性等に関する具体的な説明がなかったこと等の事情から、更新を期待することについて合理的な理由がないとは言えないとしたうえで、当該従業員の勤務成績、態度、能力、能率および作業状況等に問題が生じているとして、雇い止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとは言えないと判断した裁判例があります(東京地方裁判所令和3年2月18日判決)。
5 労働条件の引き下げと雇い止め
有期雇用契約の更新にあたり、企業側が従前よりも低い労働条件を提示し、労働者側がこれを拒絶したために雇い止めをする、という事例も散見されます。
この場合、提示した労働条件いかんにより、雇い止めの客観的合理的理由および社会通念上の相当性が認められないとされることがありますので、ご注意いただきたいと存じます。
裁判例では、60歳で定年後再雇用した従業員の雇い止めの事案で、更新されると期待することに合理的理由があるとしたうえで、企業側が提示した労働条件について、①第1案および第2案では就労時間の減少により給与総額が従前の約19万円から3万円ないし4万5000円減少し、定年後再雇用時点で定年退職時の6割程度とされた給与をさらに減額する案であり、②第3案では給与額に変動がない一方で、就労場所が変わるなど通勤等の条件が悪化し、③3案とも具体的な変更の理由が明らかでなく、当該従業員がこれを拒絶することには相応の理由があり、企業側としても当該従業員による拒絶を十分想定し得たことを考慮し、当該従業員がこれらの提案を受け入れなかったためになされた雇い止めには客観的合理的理由があるとは言えないとした裁判例があります(広島高等裁判所令和2年12月25日判決)。
6 弁護士にご相談ください
以上のとおり、定年後再雇用の従業員の雇い止めをする際には、更新を期待することの合理的理由(労働契約法19条2号)の有無、そして雇い止めの客観的合理的理由および社会通念上の相当性の有無が問題となり、個別の事案ごとに慎重な判断が必要となります。
雇い止めの判断にお困りの企業様、あるいは雇い止めをめぐるトラブルをお抱えの企業様がいらっしゃいましたら、労務問題に関する経験が豊富な当事務所の弁護士にご相談いただければと存じます。
記事作成弁護士:木村哲也
記事更新日:2025年4月16日
「当事務所」の弁護士へのお問い合わせ方法
当事務所では、地域の企業・法人様が抱える法的課題の解決のサポートに注力しております。
お困りの企業・法人様は、ぜひ一度、当事務所にご相談いただければと存じます。
・お問い合わせフォーム:こちらをご覧ください。
上記のメールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
上記のメールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。